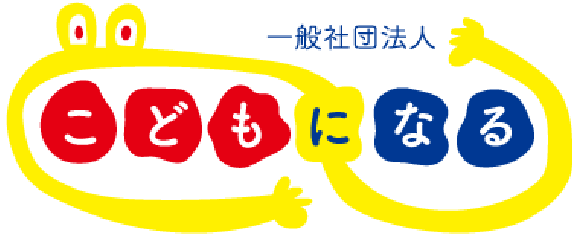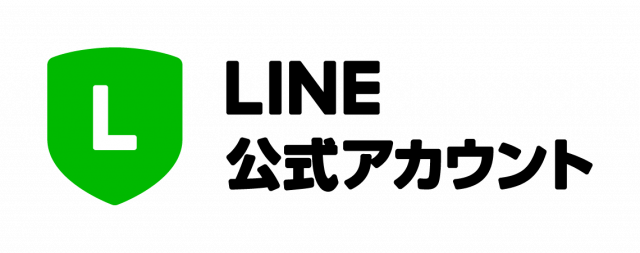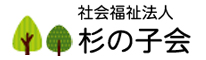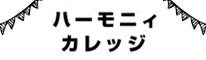先週「弱さを光に」というテーマで
親御さんだけでなく、そう診断された御本人、学校の先生、薬剤師さん、いろんな分野を学ばれておられる方、保育士さん…
皆さんにお伝えした
私の経験の中での想いを残しておきます。
「発達障がいは個性」というコトバが一人歩きしている気がします。
その個性の為、その人が生き辛くなっていても、そう言えるのかな。
◆まわりの理解と支援で「個性」になるかもしれない◆
そう思うようになりました。
「個性」ってコトバ自体が曖昧で…
私が当事者だったら、そんな風に言われても納得なんてできない。
「障がいを受け入れて」って言われて
心から受け入れること、コトバではそう言えても。
受け入れることできない、が心の声だと私は思います。
でも、向き合いたいって思う時がくるかもしれない。
我が子を想う気持ち、自分を想う気持ち、人を想う気持ちは
コトバで納得できたら楽だけど
そんな浅いものではないと、思うのです。
人が生きやすくなる為に、何ができるかな。
結局、そこに返ります。
生きにくいと感じていたら
SOSを出してくれたら、その人にはなれませんが…寄り添いたい。
一人ひとりにとって、そんな存在ほど心強いものは無い。
私もピンチの時は、SOSを出せばいいのか!って
シンプルな想いになります。
寄り添いたいと言う自分もおこがましい…
いろんな状況の方たちとかかわる中で、そう感じる時もあったけど
誰も寄り添えなかった結果、命が消えた時もある。
後悔しか残りません。
発達障がいは、見えにくいです。
まわりの無理解により、不登校・非行・神経症・ひきこもり・鬱etc.
その次の障がいに繋がるケースも大きい。
学校の先生が
教育現場の予算や制度や現状に縛られ…想いだけでは難しい面があること。
率直に伝えてくださり、痛感します。
絵本「たっちゃんぼくがきらいなの~たっちゃんは自閉症~」
私は保育士になってからずっと
子どもにも、大人にもこの絵本を読み聞かせしています。
私がコトバにできない想いをいつも届けてくれるからです。
一人ひとりが少しでも生きやすくなれたらいいな!
統合保育の中で、弱さを抱える子たちに対して、その弱さにとって伝わりやすい保育内容(マカトンサイン・次の行動をカードや写真、実物を見せて伝えるetc.)
それらも少し紹介しました。
保育が必要な人のところへ届ける保育士
大阪市淀川区十八条(お問合せ)
- トップページ
- >
- さな日記
◆発達障がいは個性ですか◆
カテゴリ : さな保育
2019-04-01 14:34:30
◆内面(心)が育つとコトバが出る◆
カテゴリ : さな保育
長年の統合保育の中で、経験しました。今も、そう信じて保育しています。
2歳児クラスで「発達遅滞」と診断された
原因わからないけど、言葉が出ない男の子の担任をしていました。
その時話す内容は、喃語程度のものでした。
不思議なもので、コトバの有無は関係なく
子どもたちのあそびは、その子の経験を広げる内容
(それが、五感に刺激を与えるあそび・昔ながらのあそびでした)
にするだけで、あそび込めました。
医療機関とも手を繋ぎ、月に一回
お母さんと私で、発達診断とカウンセリングへ。
年長クラスになる頃、3歳児程度の言葉のやりとりができるようになりました。
彼は
運動面の発達もゆっくりでしたが…
この保育内容やお母さんの「経験を広げてあげたい想いとかかわり」
によって、脳を使う
2歳児クラスで「発達遅滞」と診断された
原因わからないけど、言葉が出ない男の子の担任をしていました。
その時話す内容は、喃語程度のものでした。
不思議なもので、コトバの有無は関係なく
子どもたちのあそびは、その子の経験を広げる内容
(それが、五感に刺激を与えるあそび・昔ながらのあそびでした)
にするだけで、あそび込めました。
医療機関とも手を繋ぎ、月に一回
お母さんと私で、発達診断とカウンセリングへ。
年長クラスになる頃、3歳児程度の言葉のやりとりができるようになりました。
彼は
運動面の発達もゆっくりでしたが…
この保育内容やお母さんの「経験を広げてあげたい想いとかかわり」
によって、脳を使う
2019-04-01 14:33:19
◆泣くことは、コトバのはじまり◆
カテゴリ : さな保育
まだコトバを話せない赤ちゃん
コトバだけでは伝えきれない乳幼児とのかかわりの中で
子どもの「泣き」に参っておられる大人の姿をよく目にします。
我が子が泣いている様子を見て
心配だったり不安だったり…泣き止ませなきゃ!と
がんばる大人の気持ちも、よくよくわかります。
人に見られてる時ほど、焦って、余計にそうなる気がします。
でも、泣き止ませようとすればするほど
悪循環に陥る経験をされるお母さんも少なくないのでは…
大人は感情をコトバで伝えることができます。
でも、まだ話す機能が未熟な子どもたちにとって
「泣くこと」は感情を伝える手段でもあります。
暑い、寒い、お腹すいた、眠い、イライラ、気持ち悪い…etc.
心地好い感情の時は
穏やかな状態で、笑みや声(喃語)も出ます。
「泣きの原因」を取り除いてあげると、穏やかになる…
小さいながらに、一生懸命コミュニケーションをとろうとしています。
コミュニケーションが
人間だけにある「本能」だとしたら
言葉が話せる人間の出発点は「泣くこと」や「笑うこと」
見えない内面を訴えることが、コトバのはじまりだと思うのです。
赤ちゃんが口元に何かくると、吸おうとするのは反射のひとつです。
そういうことも、すべてコトバ(発音)に繋がっていると思うと
「泣き」も必要なことと捉えることができます。
(子どもの発達を学び、以前書いた「後退も成長と捉える」
自分の保育の軸がみえてから、子どもの泣きに…ビビらなくなりました(^-^;))

コトバだけでは伝えきれない乳幼児とのかかわりの中で
子どもの「泣き」に参っておられる大人の姿をよく目にします。
我が子が泣いている様子を見て
心配だったり不安だったり…泣き止ませなきゃ!と
がんばる大人の気持ちも、よくよくわかります。
人に見られてる時ほど、焦って、余計にそうなる気がします。
でも、泣き止ませようとすればするほど
悪循環に陥る経験をされるお母さんも少なくないのでは…
大人は感情をコトバで伝えることができます。
でも、まだ話す機能が未熟な子どもたちにとって
「泣くこと」は感情を伝える手段でもあります。
暑い、寒い、お腹すいた、眠い、イライラ、気持ち悪い…etc.
心地好い感情の時は
穏やかな状態で、笑みや声(喃語)も出ます。
「泣きの原因」を取り除いてあげると、穏やかになる…
小さいながらに、一生懸命コミュニケーションをとろうとしています。
コミュニケーションが
人間だけにある「本能」だとしたら
言葉が話せる人間の出発点は「泣くこと」や「笑うこと」
見えない内面を訴えることが、コトバのはじまりだと思うのです。
赤ちゃんが口元に何かくると、吸おうとするのは反射のひとつです。
そういうことも、すべてコトバ(発音)に繋がっていると思うと
「泣き」も必要なことと捉えることができます。
(子どもの発達を学び、以前書いた「後退も成長と捉える」
自分の保育の軸がみえてから、子どもの泣きに…ビビらなくなりました(^-^;))

2019-04-01 14:32:24